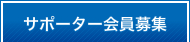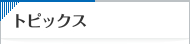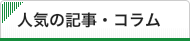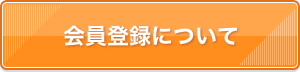関東地方整備局では、ICTの導入や意識は大手と中小企業で二極化している状況と認識している。また国、都県、市町村など発注者によっても状況は異なっている。受発注者ともに意識のハードルを下げる必要があるのではないだろうか。
同局は本年度からi-Constructionモデル事務所に甲府河川国道事務所、サポート事務所として甲府をはじめ10事務所を特定するなど支援体制を整えている。「良い取り組みなので、支援・指導・協力が図れれば」と語る。さらに「大手は独自に取り組んでおり、問題は中小企業にいかに普及させるか」と捉えている。
ICT活用について「新しい技術はとっつきにくいところもあるようだが、まずは使っていただくことが重要」と話す。国が発注する上で「他の発注者の先頭に立ってという意識で取り組んでいく」と意欲を示す。
一方、受注者からは「将来を見据えICTの件数が増えるのは業界にとって良いこと。しかし機械費が工事費に見合っておらず、ICT運用に見合った工事費を設定してほしい」といった声も聞かれる。
同局ではICT活用工事として5つの項目を設定している。必要経費は発注者指定型については当初設計で計上、施工者希望I型および施工者希望Ⅱ型は変更計上を行う(一部除き所定の条件を満たす場合)。型式により異なるものの、総合評価落札方式や工事成績で加点対象とするなど「インセンティブを設けている」という。またICT施工実績のない企業が技術支援を希望できる施工者希望Ⅱ型の3Dチャレンジ型について、本年度からICT土工を対象に試行実施する。

さらに現場支援型モデル事業として、2017年度は茨城県内で宅地造成工事(D・F街区)、18年度は栃木二宮線の道路改良工事(栃木県)を対象として行われた。18年度の工事ではICT建機により6%のコスト削減が図られ、作業人工も7割近い削減を試算した。施工者からは「ICTを導入した結果、手戻りと確認が効率化した」との声が寄せられたという。19年度は長野県高山村の砂防工事で行う。
実績がなかった中小企業でも、いざ使ってみると効果が上がり、2回目、3回目につながることもある。また同局をはじめ、1都8県5政令市、高速道路会社など21機関で構成する関東i-Construction推進協議会を設置し、推進・拡大に向けた体制を構築している。協議会において、情報共有や取り組み状況の確認などを行っているが「受注者だけでなく自治体によって熱意の有無が感じられることもある」ことが課題だ。受発注者双方で、まずは取り組んでみることが大事になるだろう。

 さらに現場支援型モデル事業として、2017年度は茨城県内で宅地造成工事(D・F街区)、18年度は栃木二宮線の道路改良工事(栃木県)を対象として行われた。18年度の工事ではICT建機により6%のコスト削減が図られ、作業人工も7割近い削減を試算した。施工者からは「ICTを導入した結果、手戻りと確認が効率化した」との声が寄せられたという。19年度は長野県高山村の砂防工事で行う。
さらに現場支援型モデル事業として、2017年度は茨城県内で宅地造成工事(D・F街区)、18年度は栃木二宮線の道路改良工事(栃木県)を対象として行われた。18年度の工事ではICT建機により6%のコスト削減が図られ、作業人工も7割近い削減を試算した。施工者からは「ICTを導入した結果、手戻りと確認が効率化した」との声が寄せられたという。19年度は長野県高山村の砂防工事で行う。