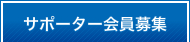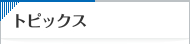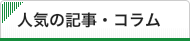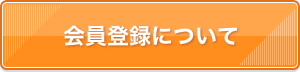将来の建設業界を担う若手の確保・育成策について、建設業振興基金の佐々木基理事長は建設業界が人材を確保できるかどうかは、建設産業の死活問題にとどまらず「日本の浮沈に関わる問題」と危機感をにじませる。今後は人材確保がさらに厳しくなることから、新しい発想と行動が必要と指摘。若い人たちに建設産業の魅力を知ってもらうためにも業界の仕事内容や処遇、キャリアパスをしっかりと提示することが重要と強調する。
◇
―担い手確保・育成の意義および現状と、課題認識について
佐々木 80年後に人口が半減すると言われる中、人材確保はどの産業にも大変な課題だ。その中でも建設業は他産業と比べて厳しい状況にある。今までと同じことを行っていたら人材の確保は難しいだろう。新しい発想と行動が必要ではないか。
建設産業は日本の成長を支え、安全・安心を確保する最も基幹的な産業と言える。建設業が持続的でないと、社会経済が成り立たなくなってしまうが、今回の新型コロナウイルスでも分かるように建設業は人がいないと、どうにもならない「リアルな産業」なので「人材を確保できるかどうか」は建設産業の死活問題にとどまらず、日本の浮沈に関わる問題と言えるのではないか。
―担い手確保・育成への取り組みとは
佐々木 「担い手をどのように確保・育成するのか」を、逆に「なぜ確保・育成ができないのか」と考えてみると、対処療法が見えてくるのではないだろうか。
若い人が業界に入ってこない、入ってきても3年で辞めてしまうという大きな原因の一つには建設の仕事がどのような仕事なのか分からないまま入ってきている点が挙げられる。せっかく建設企業に入っても短期間で辞めてしまう人は、その理由として、実際に働く中でイメージと現実との乖離(かいり)が大きかったことを挙げる人が多い。
さらに、自分が今後どのようなキャリアパスを通っていくのかが見えてこないということも離職する大きな原因のようだ。まずは子どもの頃から建設の仕事に馴れ親しんでもらうと共に、若い人たちには建設産業の魅力を感じてもらうことが重要だ。そのためには仕事内容や処遇、キャリアパスなどをしっかり提示してあげるべきだろう。
―戦略的な展開を実践するには何が必要か
佐々木 一企業では難しいため、協会活動に大いに期待したい。例えば、教育委員会との大枠の連携は国交省にやってもらい、個別の接触は各協会で行い、必要な情報提供は私ども建設業振興基金が行う。そして各企業が具体的実行の主体となる、というようにそれぞれが主体となってできることがある。自分ができることを各自が行い、それらが総合的に連携されると、業界全体の魅力発信につながるのではないか。
―建設キャリアアップシステム(CCUS)について
佐々木 持続可能な産業を作っていくためには職人の方々が誇りを持って働ける環境を作っていかなければならない。CCUSは、自分のキャリアを記録し、その積み重ねてきたキャリアが評価される仕組みであり、いわば職人としての証明書のようなものだといえる。
―CCUSの利点は
佐々木 退職金が漏れることなく積み上がっていくことになるし、現場に持ち込まなくてはならない膨大な労働安全衛生上の書類も軽減されることになるだろう。事業者にとっては現場管理の効率化が図られることは間違いないが、例えば感染症防止などへのさまざまな活用も考えられ、生産性向上のための大きなツールになると考えている。技能については適正な評価はやがて処遇と連動していくことになるだろう。現在CCUSの登録者数は技能者が40万人を超えたが、CCUS登録者がさらに増えることにより付加されるサービスも増え、メリットも大きくなると考えている。
CCUSは職人の価値の向上とそれによる建設業の魅力向上が相乗効果を発揮することで、ますます大きな意味を持ってくると思う。
―CCUSの普及に向けて
佐々木 まずは建設産業の基本的制度インフラとして発注者から元請け・下請け・労働者に至るまで理解していただき、普及するよう努めていきたい。そう遠くない将来にはカードリーダーで認証しなくても、顔認証やスマートフォンを持っていれば自動カウントできる環境ができ、使いやすさも格段に向上していくと思う。さらに普及が進み標準的な装備になってくれば、民間の知恵でさまざまな付加価値が追加されていくことも期待したい。
―最後に
佐々木 建設業は魅力ある産業のはずだが、誰が言ったか3K(危険・汚い・きつい)のイメージキャンペーンに負けてきてしまった。どの産業にも厳しさはあるが、そもそも業界環境は近年大きく改善されてきている。「危険」と言われるが、フルハーネス着用をはじめ、安全教育に力を入れている。「汚い」という点では、女性が働けるような環境になってきている。「きつい」ではパワーアシストスーツなどの導入も進んでいる。
建設業の弱点を克服するような知恵は、どんどん出てきており、もはや3Kと言われる時代ではないと言っていいと思う。給料が高く休暇がとれ希望が持てる、新3K時代の建設業の魅力をどんどん発信していきたい。
 将来の建設業界を担う若手の確保・育成策について、建設業振興基金の佐々木基理事長は建設業界が人材を確保できるかどうかは、建設産業の死活問題にとどまらず「日本の浮沈に関わる問題」と危機感をにじませる。今後は人材確保がさらに厳しくなることから、新しい発想と行動が必要と指摘。若い人たちに建設産業の魅力を知ってもらうためにも業界の仕事内容や処遇、キャリアパスをしっかりと提示することが重要と強調する。
将来の建設業界を担う若手の確保・育成策について、建設業振興基金の佐々木基理事長は建設業界が人材を確保できるかどうかは、建設産業の死活問題にとどまらず「日本の浮沈に関わる問題」と危機感をにじませる。今後は人材確保がさらに厳しくなることから、新しい発想と行動が必要と指摘。若い人たちに建設産業の魅力を知ってもらうためにも業界の仕事内容や処遇、キャリアパスをしっかりと提示することが重要と強調する。