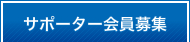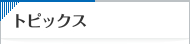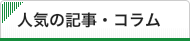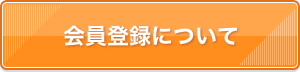2001年1月の省庁再編により建設省、運輸省、国土庁、北海道開発庁が統合し国土交通省が発足してから6日で20年が経過した。この20年間は政権交代、重要な法律の施行、多発する大規模自然災害、リーマン・ショック、新型コロナウイルス感染症など大きな事象が発生。特に災害の関係では数々の豪雨、台風、地震、火山などによって、各地でこれまでに経験したことがない被害が生じたが、国交省が先頭に立って災害復旧・復興に当たってきた。また、各種インフラの整備や新たなまちづくりが着実に進むなど、4省庁の統合による総合力を発揮した効果が確実に表れている。
20年間における主なインフラの整備状況を見ると、三大都市圏環状道路整備率は05年の約40%から19年には80%を超え、直轄管理区間の河川堤防整備率、整備新幹線の整備延長も年々増加している。01年度の建設投資は約61兆円でピーク時から減少傾向にあり、11年度には約42兆円まで落ち込んだが、その後は増加に転じ、20年度は約55兆円にまで回復する見通しだ。
4省庁統合のメリットを発揮した施策例では、羽田空港再拡張事業において、D滑走路で多摩川の通水性を確保するため航空局と河川局(当時)が連携し、人工島と桟橋のハイブリッド構造による施工を実現。年間発着枠は30・3万回から44・7万回に増加した。
また、「コンパクト+ネットワーク」の推進により、各地域内の各種サービス機能を集約するとともに、各地域を交通や情報通信等のネットワークでつなげることで一定の圏域人口を確保し、生活に必要な機能維持を図っている。
踏切対策に当たっては、鉄道局・道路局・都市局の連携により、踏切安全通行カルテの作成、カラー舗装から連続立体交差化まで段階的かつ一体的な取り組みを進め、踏切事故件数を半減させた。
他にも気候変動に伴い自然災害が頻発化・激甚化する中にあって、国交省等の職員で構成するTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の発足に伴い、災害時には社会資本整備や交通など被災自治体への集中的な支援が可能となった。
新型コロナへの対応やデジタル化の進展など新たな課題が浮上する中、国民の命と暮らしを守ることを使命とする「国土交通省」は、引き続き重要な役割を担うことになりそうだ。
 2001年1月の省庁再編により建設省、運輸省、国土庁、北海道開発庁が統合し国土交通省が発足してから6日で20年が経過した。この20年間は政権交代、重要な法律の施行、多発する大規模自然災害、リーマン・ショック、新型コロナウイルス感染症など大きな事象が発生。特に災害の関係では数々の豪雨、台風、地震、火山などによって、各地でこれまでに経験したことがない被害が生じたが、国交省が先頭に立って災害復旧・復興に当たってきた。また、各種インフラの整備や新たなまちづくりが着実に進むなど、4省庁の統合による総合力を発揮した効果が確実に表れている。
2001年1月の省庁再編により建設省、運輸省、国土庁、北海道開発庁が統合し国土交通省が発足してから6日で20年が経過した。この20年間は政権交代、重要な法律の施行、多発する大規模自然災害、リーマン・ショック、新型コロナウイルス感染症など大きな事象が発生。特に災害の関係では数々の豪雨、台風、地震、火山などによって、各地でこれまでに経験したことがない被害が生じたが、国交省が先頭に立って災害復旧・復興に当たってきた。また、各種インフラの整備や新たなまちづくりが着実に進むなど、4省庁の統合による総合力を発揮した効果が確実に表れている。