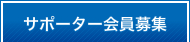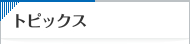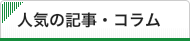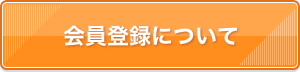赤羽一嘉国土交通大臣と日本建設業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、全国中小建設業協会(全中建)、建設産業専門団体連合会(建専連)の建設業4団体は11月30日、防災・減災、国土強靱化の取り組み推進や建設キャリアアップシステム(CCUS)のさらなる普及・促進に向けた意見交換を行った。赤羽大臣は国土強靱化等に必要な予算の確保に努める姿勢を見せたほか、CCUSの普及に向けて、2021年度から国直轄工事等でのCCUS活用工事の対象拡大と、公共事業労務費調査におけるCCUS登録者の賃金実態調査を指示したことを伝えた。また現状で建設業界の「施工余力」に問題がないことを国交省と各団体が確認した。
冒頭、赤羽大臣は建設業が社会資本整備の担い手であると同時に、災害時には最前線で「地域の守り手」として重要な役割を担っていることに感謝しつつ、コロナ禍においても「3密」対策を徹底しながら建設工事の着実な継続を求めた。
CCUSに関しては、3月にまとめた官民施策パッケージに業界を挙げて取り組んでいることに感謝しつつ「まだ発足間もないとはいえ、事業者の登録数も就業履歴蓄積数も総定数を大きく下回っていることについて危機意識を持たねばならない。なぜ登録が進まないのか、現場の声に真摯(しんし)に耳を傾けて、さらなる普及促進に向けて取り組みを深化させていきたい」と説明。21年度からの建退共におけるCCUS活用の本格実施や国直轄工事等での対象拡大、市町村を含む地方自治体発注工事のCCUS活用の働き掛けを強化する考えを示した。独立行政法人や特殊会社等に対しても活用を要請しており、UR都市機構、水資源機構、高速道路会社では検討が進んでいる。
施工余力の関係では、現下の状況として建設技能者の過不足率が落ち着き、ICT施工の増加等により施工効率が向上しているため、赤羽大臣は「施工余力に問題はないと考えている」と述べた。各団体も業界の実態として施工余力に問題がないことを伝え、さらなる公共事業費の確保を求めた。
意見交換では、CCUSに対して各団体から、直轄工事だけでなく地方自治体発注工事を含めて義務化・推奨モデル工事を進めるなど、より一層裾野を広げる必要があるとの声が相次いだ。赤羽大臣も「前を向いて頑張ろうという仕組みにならないといけない。国も本気になって動いていることを示す必要がある」との考えを伝えた。
 赤羽一嘉国土交通大臣と日本建設業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、全国中小建設業協会(全中建)、建設産業専門団体連合会(建専連)の建設業4団体は11月30日、防災・減災、国土強靱化の取り組み推進や建設キャリアアップシステム(CCUS)のさらなる普及・促進に向けた意見交換を行った。赤羽大臣は国土強靱化等に必要な予算の確保に努める姿勢を見せたほか、CCUSの普及に向けて、2021年度から国直轄工事等でのCCUS活用工事の対象拡大と、公共事業労務費調査におけるCCUS登録者の賃金実態調査を指示したことを伝えた。また現状で建設業界の「施工余力」に問題がないことを国交省と各団体が確認した。
赤羽一嘉国土交通大臣と日本建設業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、全国中小建設業協会(全中建)、建設産業専門団体連合会(建専連)の建設業4団体は11月30日、防災・減災、国土強靱化の取り組み推進や建設キャリアアップシステム(CCUS)のさらなる普及・促進に向けた意見交換を行った。赤羽大臣は国土強靱化等に必要な予算の確保に努める姿勢を見せたほか、CCUSの普及に向けて、2021年度から国直轄工事等でのCCUS活用工事の対象拡大と、公共事業労務費調査におけるCCUS登録者の賃金実態調査を指示したことを伝えた。また現状で建設業界の「施工余力」に問題がないことを国交省と各団体が確認した。